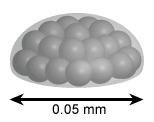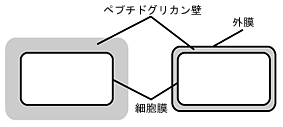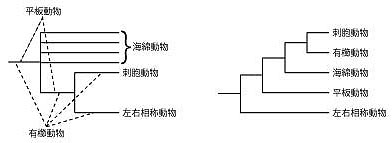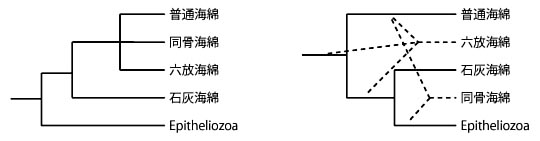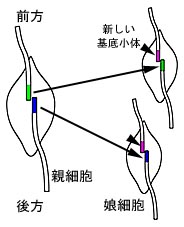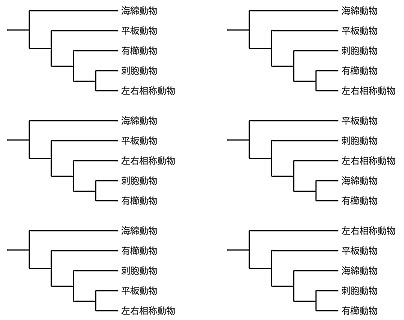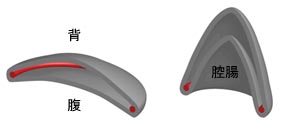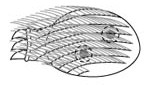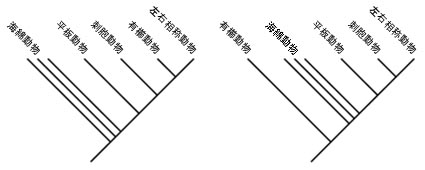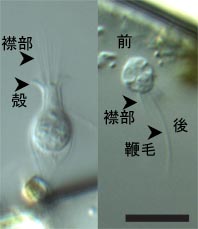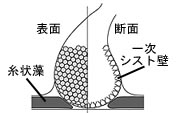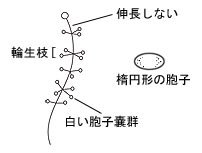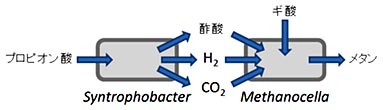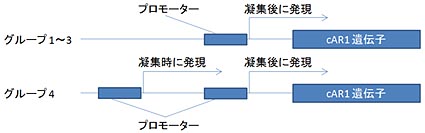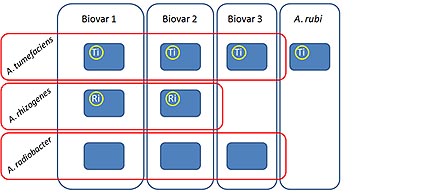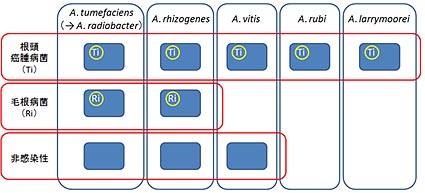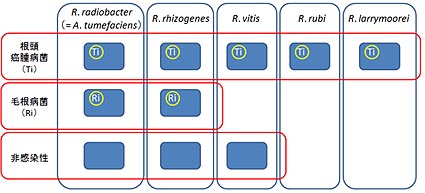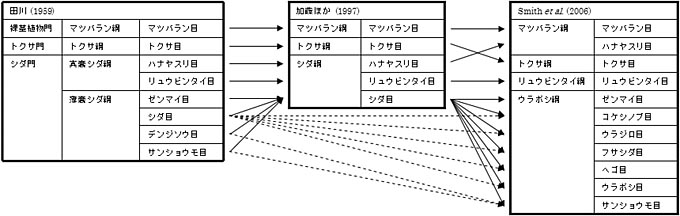���ފw�̍��{�I�ȉۑ�̈�ɁC��Ƃ͉����H�C�Ƃ�����肪����܂��B
���ɖ����I�ȕ���ɂ���đ��B���鐶���C�Ⴆ�Ό��j�����ł͉��������ē����܂��͕ʎ�Ƃ���̂��͓��ł��B
DasSarma & DasSarma (2008) �͍��x�D���ۂ� Halobacterium ���̎핪�ނɂ��Ė���N���Ă��܂��B
���x�D���ہiextreme halophiles�j�� 1.5�i2.5�j�`5.2 M�̐H���iNaCl�j�̑��݉��ł̂ݐ���ł�����������w���C
�S�ČÍۃh���C���̃����A�[�P�I�^��n���o�N�e���E���j�n���o�N�e���E���ڃn���o�N�e���E���Ȃɏ������܂��B
�����Ē��҂�̒��ڂ��Ă��� Halobacterium �����̃^�C�v���ł��B
Grant (2001)�CGruber et al. (2004)�CYang et al. (2006) �𑍍�����ƁCHalobacterium
�ɂ͂���܂� 15 �킪�L�ڂ���Ă��܂������C3 ��������đS�ăV�m�j���i�ٖ��j���ʑ��ɂȂ��������ł��B
���͂����̕����� H. salinarum �Ƃ���Ă����ł��B���̎�ɂ� H. halobium ��
H. cutirubrum ���ٖ��Ƃ��Ċ܂߂��Ă��܂����C���҂�͋������� 3 ��Ƃ���Ă�������
1 ��ɂ܂Ƃ߂邱�ƂɈ٘_�������Ă��܂��B
�����ł͓��� 3 �̊��𒆐S�� Grant (2001)�CGruber et al. (2004)
�ƒ��҂�̌����ɂ��Č������Ă݂����Ǝv���܂��BH. salinarum �̃^�C�v���� DSM 3754
�i=ATCC 33171�j�ŁC���ꂪ "�^��" H. salinarum �ɂȂ�܂��B����Ń��f�������Ƃ��Ďg�p����C
�Q�m����ǂ��s���Ă���̂� NRC-1 ���� R1 ���ł��i����������� H. salinarum�j�BNRC-1
�i=ATCC 700922�j���� H. halobium �ɓ��肳��Ă������ŁC��� H. salinarum �ɍē��肳��܂���
�i�Q�m����ǂɒx�ꂽ�����j�B������ R1�i=ATCC 29341 =DSM 670�j��������
H. halobium �ɓ��肳��Ă������ŁC���X�K�X�E�i���f�K�X��~�ς��čזE�ɕ��͂�^���鏬�E�j
�������ψّ̂Ƃ��đ��̊�����Ƃ�ꂽ���̂ŁCNRC-1 �����e���ł���Ɛ��肳��Ă��܂��iGrant, 2001�j�B
�ʂ����Ă����̊��͓���ɕ��ނ����ׂ��Ȃ�ł��傤���B
Gruber et al. (2004) �� NRC-1 ���� H. salinarum �ɓ��肷��ۂɁC�{����Ē�`���C
�^�C�v���� NRC-1 ���̐����w�I����i�\���^�j���ǂ���v���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B
�Ƃ��낪���҂�͍R�̑ϐ��}�[�J�[�C�זE���̗z�C�I���C�זE���̃^���p�N���C�����C���̑g�����^�C�v����
NRC-1 ���Ȃǂ��ꂼ��̊��ԂňقȂ邱�Ƃ��������Ă��܂��B���ɖ��m�ȕ\���^�̍��Ƃ��āC
R1 ���ɂ�����K�X�E�����@�������C���ꂪ�{���̐�����̓����f���Ă���\�����w�E���Ă��܂��B
������ R1 ���͓ˑR�ψي��ł���C���������K�X�E�̗L���̓v���X�~�h��̕s����ȗ̈�ɂ���Č��܂��Ă��邽��
�iGrant, 2001�j�C���̍�����Ԃ̍��̋c�_�Ɏ������ނ��Ƃɂ͋^����o���܂��B
��`�^�Ƃ����Ӗ��ł́CGruber et al. (2004) �̓^�C�v���� NRC-1 ���Ƒ� 1 ���� 16S rRNA �̗ގ�����
97.1%�u���v���邱�Ƃ��������Ă���̂ɑ��āC����̒��҂�͂قڑS�Ă̊����u�Ⴂ������v
���Ƃ��������Ă��܂��B�܂����҂�͑��̈�`�I�ȈႢ�C���� rep-PCR �Ō��o�����Ⴂ�������Ă��܂��B
rep-PCR �́C�J��Ԃ��z��ɐv�����v���C�}�[�� PCR ���s���C�J��Ԃ��z��Ԃ̑����̃Q�m���f�В����r����C
�����̓���̂��߂̎�@�iCleland et al., 2008�j�ł��B���̌��ʂ� DSM 3754 ���CNRC-1 ���C
R1 �����܂ނقƂ�ǂ̊��ԂňقȂ��Ă��邻���B������ rep-PCR �͌��X�قȂ��C
������ʂ��邽�߂ɊJ�����ꂽ��@�ł��̂ŁC���̈Ⴂ�̒��x���퍷�Ƃ��ĉ��߂���̂͐����ł͂Ȃ��ł��傤�B
�����Ƃ��C���̌��ʂ� R1 ���� NRC-1 ���ɗR������\���ɋ^���悵�Ă���_�͒��ڂ���܂�
�iR1 �����ˑR�ψي��ł��邱�Ƃ�ے肷����̂ł͂���܂��j�B
�������ċc�_���r���Ă݂�ƁCH. salinarum �� 1 ��ƔF�߂闧��iGrant, 2001;
Gruber et al., 2004 �Ȃǁj�ƍ���̒��҂�̌����͐��|���_�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂�
�i�Ƃ����Ă�����̒��҂�͎핪�ނ̉���Ă������Ă��Ȃ����߁C���p�����Ȃ��j�B
���̏œ_�́u�ǂ̒��x�̍�������Εʎ�Ȃ̂��v�Ƃ������ɋA������Ǝv���C
�����ɖ����I�ɑ����鐶���ɋ��ʂ̖�肪�����Ă��܂��B������ Halobacterium �̏ꍇ�ɂ́C
Ottawa �� National Research Council�iNRC�j�����̈ێ����~�������߂ɁC�����̊��������C
���邢�͊��̗R�����s���ɂȂ������߂ɖ�肪����ɕ��G�ɂȂ��Ă��܂��iGrant, 2001�j�B
���ǁC����ł͜��ӓI�ł��邱�Ƃ�F��������ŁC�Ȃ�ׂ����m�ɋ߉���Ƌ�ʂł���\���^�i�̑g�ݍ��킹�j
�Ɋ�Â��Đ��������s�����Ƃ��K�v�ł���Ǝv���܂��BGruber et al. (2004)
�̕��ނ͂��̓_�őÓ��ł��傤�B�����[�����Ƃɔނ�͍זE�S�̂̃^���p�N���̓d�C�j�����̗ގ������C
DSM 3754 ���� NRC-1 ����Ƃ��������ɋ����Ă��܂��B��ʓI�Ȕ�r���s���Ă��Ȃ����߁C
���̌�̉��P�̗]�n�͂���܂����C�^���p�N���̑g���Ƃ����u�\���^�v�ɒ��ڂ����핪�ނƂ��āC
���[�����������҂������Ƃ���ł��B
�]�k�ł����C�w���Ɋւ��c�_�ɂ��ĐG��Ă��������Ǝv���܂��B���҂�̈ӌ��ł́C�Íۂ̒��Ԃ�
Halobacterium �Ƃ������O�͕s�K���ŁC������ Haloarchaeum �Ɖ����C
�����ĉȖ���ږ��Ȃǂ��ύX���C�ʏ̂� "haloarchaea" �Ƃ���C�Ƃ��Ă��܂��B
����������͖����K��̐��_����͐�ɋ�����Ȃ���Ăł��B���ۍۖ����K��̋K�� 55 (1) �ɂ́C
�u���@���v���u�s�K���ł���v�Ƃ́u���R�����Ŋ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ɩ�������Ă���
�i���ۍۖ����K�� 1990 �N�Ŗ|��ψ���, 2000�j�C���҂�̌������́i�ʏ̂ɂ��Ă͕ʂƂ��āj
������������̂ł͂���܂���i���������Ύ����悤�ȉ������������C
���j�����̊w���S�̂ɑ傫�ȍ����������܂��j�B���̑��CH. salinarum �� H. halobium
������ꍇ�C��҂ɗD�挠������Ƃ̌��������p���Ă��܂����C���̓_�͊m�F�ł��܂���ł���
�i�����炭 H. salinarum ���������GGrant, 2001�j�BH. salinarum �̒Ԃ�ɂ��Ă�
H. salinarium �̕����������ƈ��p���Ă��܂����C����͕��@�I�ɂ͂ǂ���Ƃ������Ȃ��悤�ŁC
�K���͒��҂̑I���ɔC�����邱�ƂɂȂ肻���ł��i�K�� 62b�j�B�܂�C����ł� H. salinarum
�ɍ��킹�Ă����Ă����ł��傤�i���҂�����̂悤�ɂ��Ă���j�B
DasSarma, P. & DasSarma, S. On the origin of prokaryotic "species": The taxonomy of halophilic
Archaea. Saline Syst. 4, 5 (2008).
Cleland, D., Krader, P. & Emerson, D. Use of DiversiLab repetitive sequence-based PCR system for
genotyping and identification of Archaea. J. Microbiol. Methods 73, 172-178 (2008).
Grant, W. D. in Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 2nd Edn. Vol. 1.
(eds Boone, D. R., Castenholz, R. W. & Garrity, G. M.) 301-305 (Springer, New York, 2001).
Gruber, C. et al. Halobacterium noricense sp. nov., an archaeal isolate
from a bore core of an alpine Permian salt deposit, classification of Halobacterium sp. NRC-1
as a strain of H. salinarum and emended description of H. salinarum.
Extremophiles 8, 431-439 (2004).
���ۍۖ����K�� 1990 �N�Ŗ|��ψ��� �� ���ۍۖ����K��i1990 �N����j
(�؍��o��, ����, 2000).
Yang, Y., Cui, H.-L., Zhou, P.-J. & Liu, S.-J. Halobacterium jilantaiense sp. nov.,
a halophilic archaeon isolated from a saline lake in Inner Mongolia, China.
Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56, 2353-2355 (2006).
�ߋ��̊֘A�L��
�Q�m����ǂɒx�ꂽ�����C
��͎��݂��镪�ޒP�ʂȂ̂��C
�P�n���Q�����ŕ��ނ͏o���Ȃ��C
�����~�h���̎�͒P�n�����H�B