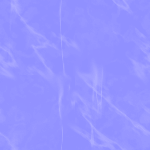
水の誘惑
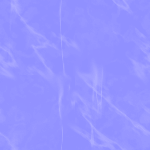
4月とはいえ、外の気温はまだ肌寒く。
健康診断を受ける生徒達も、ジャージ着用の者が多い。
そんな生徒達の中に、梧桐勢十郎の姿は無かった。
学生ならば誰もが絶対に受けさせられるはずの健康診断を、一人受けない。
その事を、一部の人間だけは不信に思っていたが、余り深くは考えなかったようだ。
本当ならば、この違和感をもっと深く追求するべきだったのだろう。
今、嘉神はそう後悔していた。
だが時は戻らない。
いや、戻った所で自分に何が出来ただろう…。
傷付かずに済むように、覚悟をすること位か。
情けないが、本当に自分には何の力もなく。
今はただ、目の前で眠る青ざめた顔を救う術を考えて。
何度も考えて、絶望していた。
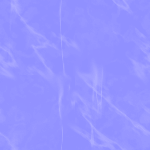
健康診断を受けないというのは、結構大変な事だった。
事情は話せない。
だからただ何かと嘘の理由を並べ立てて、教師を黙らせるしか方法が無かったのだ。
窓から生徒達の姿を見ている梧桐は、一般生徒にはそれでも相変わらず強く恐い存在に映っただろう。
だがその当人は、ぼんやりと思い出していた。
今までは思い出す事の無かった、遠い遠い日々を――。
あの頃はこの行事、健康診断が好きだった。
地味で「行事」とも言い難いものではあるが、それでも好きだった。
だって自分が誇らしかった。
何の問題もない自分が証明されるのだ。
だがそれとは正反対に、この行事を嫌いだと言う少年に出会った。
「受けたくない」と呟いた、その彼を梧桐は不思議に思ったが。
その理由はすぐに分かった。
彼は健康ではないのだ。
身長は梧桐と同じくらいだったが、体重は随分と少なかった。
いつもしていた妙な咳も、何かの病気によるものらしい。
「いい加減に医者へ行け」と診断の数日後、教師に諭されていた。
梧桐には不健康な人間というものが良く理解できなかった。
怪我は良くするが、病気になるというのはどういった苦しみを伴うのか…。
全く分かっていなかった。
だから彼をからかった。
「病弱なサルめ!」と。
「オレの勝ちだ!」と。
今思えば、その言葉に彼は傷付いたのかもしれない。
だが、結果として、そのからかいは良い方向へと効を成した。
からかわれ悔しく思った彼は病院へ通い出し、1年後の健康診断ではほぼ健康と診断された。
それでも梧桐は「身長が2センチ勝っている」だの「何だその弱々しい体重は」などといちいち彼を構った。
負けず嫌いな彼は、サボりがちだった道場にも真面目に通い出し、いつしか本当に健康になった。
そして、強くなった。
梧桐がそんな事を思い出していると、その想いの当人が目に映った。
彼、半屋工は今年も健康だと診断されるのだろうか。
あいかわらず面倒そうにレントゲン車の列に並ぶその姿に、梧桐はふっと笑った。
そう、自分はこうして思うがままに半屋工を強くして。
そして弱くもした。
その事を今、梧桐は深く深く後悔している。
どうすればいいのか。
どうするべきなのか。
梧桐は昨日、一晩中その事に苦悩した。
そして今日、覚悟を決めて登校した。
今日、梧桐は「オレのもの」に別れを告げる。
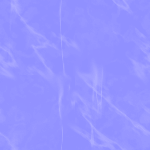
「サル!」
下校するため門を出ようとしたところで、聞き慣れた声に不本意な呼び方で呼ばれた。
もちろんいつもの様に腹は立った。
だが今日の半屋は熱くなって掴みかかったりはせず、ゆっくりと振り向いた。
「何か用かよ…。」
その声にはいつもの様な力がない。
梧桐はその理由に気が付いていた。
昨日の…。
昨日のオレの言葉に、おまえは戸惑っているのか。
どういう意味かわからず…。
オレの気持ちがわからず…。
自分でしている事とはいえ、胸が痛んで仕方がない。
本当ならばこんな事は…。
こんな事はしたくはない。
本意じゃないのだ。
本心じゃないのだ。
昨日オレが言った言葉。
これからおまえに告げる事。
きっと全てがおまえを壊すだろう。
この衝撃に耐えうる程には、まだおまえは強くなりきれていない。
ずっと傍にいて、オレがおまえを強くしていくはずだった。
一緒に、
生きていきたかった。
それなのに、
それなのに何て遠慮もなく、
オレはこんなものに冒されてゆくのか…。
「オイ」
思考に飲まれた梧桐の意識を半屋の声が呼び戻した。
気が付けば、見慣れた彼の顔が近くなっていた。
その薄茶の双眸が真っ直ぐに梧桐を見つめる。
「話がある。」
その瞳に全てを見透かされないように、力強くそれだけを告げて。
梧桐は半屋の手を引いた。
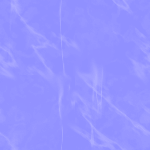
熱い手だった。
この何年もの間、梧桐の手は幾度となく半屋に触れたというのに。
それなのに今、繋がれた手の熱さに半屋は驚いていた。
そう。
昨夜もオレに触れたこの手。
いつも強引にオレを組み敷くその腕が、更に乱暴に感じられた夜。
「半屋…。」
いつもの威圧感が感じられない、囁くような呟くような小さな声でオレを呼ぶ。
何度も何度もオレを呼ぶ。
縋り付かれているようだった。
誰か知らない別の人間に見下ろされているようで、吐き気がした。
余裕がない。
そう感じた。
普段は強引でも無理はさせなかった。
オレが嫌がる事はしない。
というよりは強要はしない。
オレが嫌がらなくなるように、ゆっくりと仕向けるような抱き方だった。
それをまるで優しさのように錯覚し、オレは結局梧桐の望み通りになる。
そんな自分は認めたくないが、それでも梧桐に抱かれているその時には抵抗しきれない。
せめて声を殺そうと必死になるが、それも叶わない。
不本意な涙が流れる。
視界が滲む。
自分の中に梧桐しかいなくなる瞬間。
「半屋……。」
また梧桐が名を呼んだ。
「半屋…何か別の事を考えているだろう。」
そう言うと抱きしめる腕に力がこもる。
更に深く繋がった痛みと、別の何かが半屋を苦しめる。
「オレの事しか考えられないようにしてやる。」
梧桐は抵抗する半屋を力尽くで自分の上に乗せた。
逃げる事も出来ず、縋る物もなく、ただ梧桐の上で耐えるしかない。
半屋が最も嫌がる形。
悔しさと不快感でまた涙が伝った。
散々振りまわされた後、脱力した半屋を梧桐が支え、別人のように優しく横たえた。
まだ涙の跡の残るその頬にそっと触れ、喘ぐその唇に深く口付ける。
「悪かった…。今日で最後だ……。」
独り言のように呟いたその言葉は何を意味をするのか。
意識の薄れていく半屋には分からなかった。
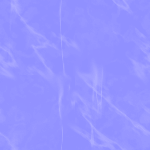
「ここまで来ればもういいだろう。」
いくら抵抗しても外せないほどがっちりと握られていた手が、あっけなく離された。
熱い手の中から解放され、半屋の手は余計に外気を冷たく感じる。
「ったく…。」
強く握られ、まだ痺れている手を解しながら。
半屋は梧桐の出方を待っていた。
無意識の内に、半屋は恐れていた。
梧桐が告ぐであろう言葉を…。
だから問わない。
問えない。
「話」の、その内容は…。
駅とは逆の、自分達を知る生徒のいない、こんな人気のない道まで。
梧桐が無言で半屋を連れてきて。
そして告げるその言葉は…。
今朝、目を覚ました半屋の隣に、やはり梧桐はいなかった。
いつもの事だ。
今までだって、梧桐は半屋よりずっと早く起きて学校へ行ってしまう。
それなのに。
いつもの事なのに、何故か半屋は不安にかられた。
「最後」という、その言葉が。
半屋を不安にさせていた。
何度も夢に見た、離れていく梧桐の背中がその時何故か瞼に浮かんだ。
「半屋。」
長い沈黙を破ったのは梧桐だった。
半屋は眼を閉じて、覚悟を決めたように
「何だ。」
とだけ答えた。
「オレはブラジルに行く。」
そう、梧桐は告げた。
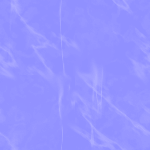
世界が赤い。
視界の全てが赤に支配されてゆく。
何も。
何も見えなくなってしまった。
何もない世界。
そう。
梧桐に出会うまで、半屋の世界には何もなかった。
大切なもの、いとおしいもの、欲しいもの、守りたいもの。
そういったものが何もなかった。
だから。
だから死んでもよかった。
命に執着などなくて…。
喘息だの何だのと、いくつもの病気が身体を蝕んでいた。
だがそれを治したいとは思わなかった。
苦しくは感じたが、別にどうでもよかった。
こうして放っておけばいつか死ぬかもしれない、そう思っていた。
ただ一つ。
ただ一つの不安だけを抱えて、何となく生きていた。
そんな半屋を梧桐は変えた。
「梧桐に勝ちたい。」
そんな単純な目標が。
「負けるのは悔しい。」
そんな単純な感情が。
半屋の世界に波を立てた。
先の見えない長い長い道。
人は誰もその道を、何かを目指して歩いて行く。
その目指すものをはっきりと意識できている人は少ないだろう。
目指す先に何があるのか、それが分からないまま生きてゆくのだ。
それが苦しい。
それが人を迷わせ、人を不安にする。
反対にその目指すものが分かっていたとしたら。
それはどんなに楽だろうか。
その目指すものに向って、無心で歩いて行けば良いのだ。
それ以外には何もいらない。
何も気にはならず、何物にも負ける事はない。
強く逞しく生きてゆける。
その事を梧桐は知っていた。
目指すもの、それは梧桐にとっては忌々しい、心底憎い存在であった。
しかし、その反面でその存在を超えるため、強くなった自分を知っていた。
それがどんな存在であっても、目指すものがあれば人は強くなれるのだ。
半屋に初めて会った時。
梧桐は何て弱々しい人間だろうと感じた。
光を感じない。
生きている人間が放つ、命の光を全く感じない。
まるで死人がそこにいるようだった。
何かを与えてやれれば良いのに―。
梧桐はそう思った。
光が見たい。
コイツが放つ光を見たい。
それはどんな輝きだろう。
どんな美しさなのだろう。
半屋はケンカで負けた事がない、と知った。
だから梧桐は半屋を煽り、ケンカをした。
半屋の目指すもの。
それが自分になれば良い。
半屋は梧桐を目指して、歩き始めた。
長い長い道を、迷うことなくただ一途に。
そして今、半屋は生きている。
最近の半屋は本当に強く優しい光を放つようになった。
その光に、梧桐はいつしか惹かれていた。
自分が導き出したその光。
人に愛される純粋なその光が、何て誇らしい。
半屋が生きていること、それが何て誇らしい。
いつまでもいつまでも。
永遠にこの光が傍にあるように。
この幸せが傍にあるように。
梧桐はそう願うようになっていた。
だから今、梧桐は半屋に背を向ける。
伝えるべき言葉がまだあるというのに。
果たすべき目的もまだあるというのに。
それでも梧桐の意志とは関係無く、身体は半屋に背を向けてしまった。
半屋を見ることが出来ない。
半屋を見ることが、恐い。
自分が大切なもの。
自分の幸せ。
それを自分で壊した瞬間。
この言葉の意味が半屋には伝わった事だろう。
ただブラジルへ行くのではない。
半屋と離れてブラジルへ行き、そして帰るつもりはない―。
二度と会わないつもりなのだと、そう別れを告げられたのだと。
半屋には伝わってしまったはずだ。
目指すべきものとして与えた自分を、この手で奪ってしまった。
道の途中で消えた目印。
半屋は…。
半屋は道を見失い、不安に襲われるのだろうか。
強くなった半屋はそれでも道を進もうとするだろう。
座りこんで諦める事はしない。
だが、手探りで生きるその不安定さ。
その辛さは半屋を苦しめ、光は失われてゆくのだろう。
光は…
失われてゆくのだろうか?
大切なもの。
壊してしまった。
その姿を見るのが恐くて、梧桐は背を向け、目を閉じる。
もう何も見たくはない。
もう何も、知りたくはなかった。
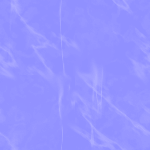
梧桐の背中が遠ざかって行く。
それは何度も見た夢と同じようで、違う。
手を伸ばせない。
足も動かない。
声が、出ない。
何も考えたくない。
この場所から早く離れたいのに、視界が赤く染まっていて何も見えない。
夕陽の色にしては濃く深すぎる赤い色。
何も見えない。
それでも道を探す。
この苦しさは何だろう。
視界に離れて行く梧桐の姿だけが妙にはっきりと映り、他には何も見えなかった。
それが、誰にも言えない、この事故の理由。
背後からの大きな音と光に、振り向いたその時にはもう、手遅れだった。
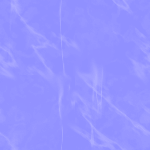
クラクションの大きな音が背後で響いた。
ほとんど距離のない、そんな感じだった。
嫌な予感。
振り向く事が怖いと感じた。
そして、水音。
一瞬遅れて振り向いたその時、背後に半屋の姿は無かった。
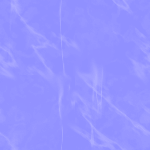
横をトラックが通って行った。
それほど大きくはないが、この狭い橋の上ではやけに大きく感じた。
だが、端に寄れば簡単に避けられる。
だからこそ、トラックもこの事故には気がつかず、通り過ぎて行ったのだろう。
反射神経に優れた半屋なら尚の事、避けるのは容易かったはずだ。
だが、いない。
立っていたはずの場所に半屋がいない。
そう、水音が。
水音が橋の下から聞こえた。
こんな予想は外れていてほしいが…。
橋の下へ目をやった。
不気味なほど赤く染まったその川の、水が不自然に揺れていた。
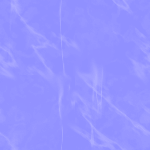
水が冷たい。
もう4月なのに。
そんなどうでも良い事を思った。
橋が低かったせいか、落ちた際の衝撃はほとんどない。
だが、冷たい水が腕を突き刺してくる。
流れて行く、赤い血液。
何処で傷付いたのかは分からないが、大きく深い傷ができていた。
このままでは多分死ぬ。
必死で足掻けば、助かるだろうか。
泳ぎは得意だし、岸までも遠くない。
そう思うが、思うだけだ。
この腕の痛みでは無理だと、自分に言い訳をしながら。
もうこのままで良いと、そう諦めた。
水に反射する夕陽の光。
その煌きや流れる血液の赤が。
綺麗だと、柄にも無く思った。
この水の中、死んでしまえれば良い。
何故だろうか、そう思った。
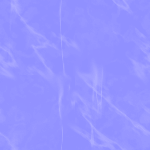
名を呼んでも、返事はない。
橋の下に降り、出せる限り大きな声で呼ぶ。
それでも流れて行くだけ。
反応を示さない。
まだ生きてはいるはずだ。
車に接触したというよりは、避けた勢いで橋から落ちたようだった。
ひどい怪我でもしていなければ、自力で助かる事も出来るだろう。
だが、助かろうという気が無ければ…。
途中まではそれほどでもないが、中心あたりは今の季節だとかなり深さがあるようだった。
あのまま気を抜けば、この冷たい水に沈むだろう。
人通りがない時間と場所を選んだ。
だから助けられるのは自分しかいないだろう。
もし誰かがいたとしても、他人を真剣に助けようと、そう思う人間だとは限らない。
自分だけだ。
自分だけが半屋を救える。
そう思うと他の事はどうでも良くなった。
迷わず水に入っていった。
自分の命など費えても良いと、そう思えた。
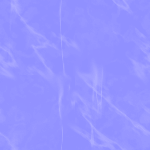
梧桐の声が聞こえた気がして目を開くと、俺に向かって泳ぐ姿があった。
俺を助けるつもりなのか。
もう会わないと、そう決めた人間なんて見捨てれば良いのに。
やがて俺の元まで泳ぎ着いた梧桐がいつもの様に俺を叱った。
梧桐の怒鳴り声。
体を支える力強い腕。
俺を見る時の困ったような視線も。
何だか全てが懐かしい。
認めたくはなかった事を気が付かされる。
昔からいつも求めていた物。
たった一つだけ必要としていた物は、この男の存在だったのだと。
そんな弱い自分に気が付かされた。
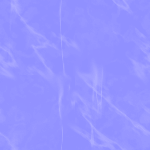
「死ぬつもりだったのか?」
何を呼びかけても反応も示さない半屋に、そう問いかける。
半屋はうっすらと頷いた。
「何故生きる事を放棄する?」
そう問うた梧桐の声は震えていた。
目眩がする。
今にも気を失いそうな自分を何とか支える。
半屋を助けるまではと言い聞かせて。
「お前は死ぬな…。お前が死んだら証が無くなる。」
ずっと悩んでいた言葉を口にして、半屋を岸に上げた。
そして、力が抜けた。
堪えていた物を吐き出してしまう。
半屋を汚してしまった事を後悔する。
目が霞んでもうその姿は見えなかったが。
自分が水に流されている事をうっすらと感じた。
半屋らしき人の姿が段々と遠くなる。
それが何よりも苦しくて、目を閉じて意識を棄てた。
もう冷たいと感じなくなったその水に、ゆっくりと沈んで行く。
1度だけ目を開くと、水面の揺らめきが見えた。
何故だか安心する。
そういえば羊水の中で母親に守られて、そして生まれ出る人間は、水の中に同じ安心感を抱くと聞いた事があった。
これがその安らぎだろうか。
何年も感じたことの無かった気持ちの良さ。
眠るように、また目を閉じた。
その目を開く事はもう2度とないだろうと、そう分かっていた。
それでも良いと、この水は思わせる。
あれだけ強く生きる事を望んでいたのに。
生きる事に疲れた様に、自ら眠りについた。
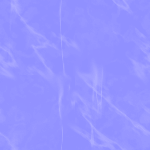
「ねぇ、嘉神君…。」
いつの間に目を覚ましていたのか。
その声に振り向くと、まだ力の無いその瞳が嘉神を見ていた。
「梧桐君…死んじゃったと思う?」
そう結論付けたくない事を口に出されて、痛いほど心臓が鳴る。
「半屋君にね、彼以外の血が沢山付いていたんだって。まるで浴びたように…。」
「八樹。」
もう止せと咎めようと名を呼ぶと、その瞳から涙が溢れた。
強い人間だと思っていた、彼が見せた涙。
それだけで、絶望感が増してゆく。
生死は分からない。
梧桐自身が発見されないからだ。
警察も必死で探しているのに、それでも見付からない。
だから生きている可能性も高い。
だが、何故かそう思えない。
川岸で発見された半屋の少ない証言からでは、警察には何も分かっていない。
一番事情が分かっていると思われる伊織佳澄の姿も行方不明らしい。
テレビの中では様々な憶測が飛び交い、友達として嘉神にも何度かマイクが向けられた。
あまりの無神経さに怒りが込み上げたが、その様子すらも喜んで映されていた。
自分よりも傷の深い、彼も同じ状況にあったのだろうか。
そう思うとこの涙が更に痛々しく感じられる。
「何も考えずに、眠っていた方がいい。」
それくらいの言葉しかかけられない。
自分の不器用さにも怒りを感じるが、それだけが原因でもない。
いくら上手く言葉を紡いだところで、誰にも彼を救えないだろう。
梧桐勢十郎という、その存在はあまりにも強かった。
自分も彼も、深い所に大きく穴が開いて埋まらない。
誰にも埋める事はできないだろう。
嘉神の言葉に、それでも彼は微笑んだ。
頷いて、背を向ける。
嘉神も背を向け、そして保健室を静かに出ていった。
お互い一人でいる方が、素直に泣いて眠れるだろうと。